
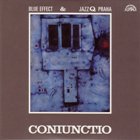
 |
Meditace | 1969 | Radim Hladik (g)率いるBlue Effect (M Efekt)の一作目。ビート、ブルース、ジャズの中間を行くような音楽性で、かつ、バックにオーケストラなども導入している。 |
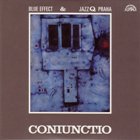 |
Coniunctio | 1970 | Jazz Q Prahaとの連名。ウッドベース、サックスなど、かなりジャズよりのロック。混沌としたところが、また、よい感じのアルバム。 |
 |
Collegium Musicum | 1970 | |
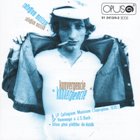 |
Konvergencie | 1971 | The Niceの様なオルガンを中心に、ギターもリードをとる大作4曲で構成したアルバム。1曲目で時折入ってくる少年合唱団のコーラスがいかにも中欧らしい。クラシカルだがオルガンの音色などかなりハード。2曲目はライブ、3曲目はいろいろなタイプの音楽が寄せ集め。4曲目は、インプロビゼーションの様。 |
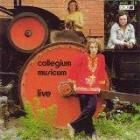 |
Live | 1973 | ライブ。キースエマーソンの様にオルガンを弾き倒す。ベースも、バリバリっとした音で、存在感を示しつつフレーズを奏でる。ラストは、火の鳥を、ドラムソロを挿入して演奏。東欧のバンドらしく、スクェアな感覚のアルバム。 |
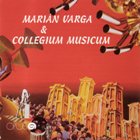 |
Marian Verga & Collegium Musicum | 1975 | キーボードはピアノ、オルガンなどを使い分け、ギターも活躍してのライブ。 |
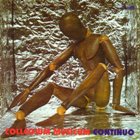 |
Continuo | 1978 | |
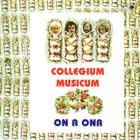 |
On A Ona | 1979 | |
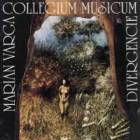 |
Divergencie | 1981 | 2枚組。従来と路線が大分変ったアルバム。洗練されたダイナミックなシンフォロックとオーケストラやコーラスを大々的に導入した楽曲が絡み合った傑作。 |
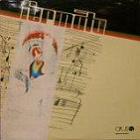 |
Fermata | 1975 | 73年に結成されたスロバキアのジャズ・ロック・バンドFermataの1作目。ヘビーでテクニカルなジャズ・ロックのアルバム。東欧系のバンドに特徴的なのだが、ベースにモワっとした重さがあり、バタートーストを食べたと思ったら、ピーナッツバターを塗ったトーストを食べてしまったような感触。 |
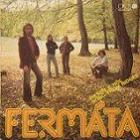 |
Piesen Z Hol | 1976 | 2nd。前作よりもシャープで、スピード感のあるベース、テクニカルなギターや、エレピなどのキーボードの音色や展開などから、Brand Xの様。バイオリンも登場し、ラストの曲などは、一瞬、PFMのjet lagなんかを思い出したりして。とても格好良い。傑作。 |
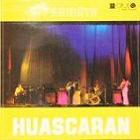 |
Huascaran | 1977 | スタジオアルバムの3作目。タイトル曲では、たおやかなバイオリンとピアノやストリグス系シンセサイザーが叙情性を引き出している。テクニカルなギター、ベースとともに緩急自在なプログレッシブ&ジャズ・ロックを展開している。なかなかよい。プログレの視点からすれば、これがFermataの最もプログレッシブなアルバムということになるだろう。 |
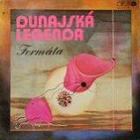 |
Dunajska Legenda | 1980 | 4th。3枚目までのような長尺曲が無くなり、概ね3〜5分程度の曲で構成されたアルバム。ピアノが美しい曲、アコースティックな曲をはじめジャズ・ロック以外の曲も結構収録されている。前作と同様にプログレ・シンフォ系のアルバム。傑作。 |
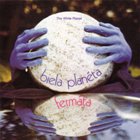 |
Biela Planeta | 1980 | 5th。バリバリのジャズ・ロック/フュージョン路線に戻った。ラスト直前の曲が、アコースティック・ギター中心の演奏なのだが、ドラマティックに盛り上げられていて、なかなかよろしい。 |
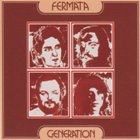 |
Generation | 1981 | 6th。本作も基本的には、高度な技術に裏付けされたテクニカルなジャズ・ロック/フュージョン路線。曲・メロは、そこそこエスニック・辺境系のものも登場するが、基本形は、かなりコアな内容。 |
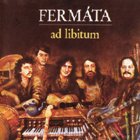 |
Ad Libitum | 1984 | 7th。いきなり歌で始まりオッと思ってしまうが、その後は安心、8分超のドラマティックな曲などいろいろ変化に富んでいる。これは、プログレ系として、結構いけるアルバムではないかと思う。 |
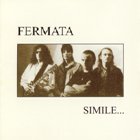 |
Smile... | 1991 | 8th。えらくシンフォニックなフュージョン風ロックだが、実は、Focus並の、なかなかドラマティックな演奏を聴かせてくれる。マケドニアのLeb i Solなどにも近いイメージ。 |
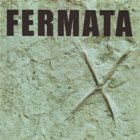 |
X | 1999 | 10th。カシオペア、Crosswindやフュージョン寄り時代のKENSOなどとも共通した、明るい、洗練されたフュージョンのアルバム。敢えてFERMATAでそれを聴かなくても良いと言えばそれまでだが、先入観無しで聴けば、それなりによい。 |
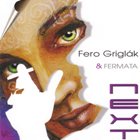 |
Next | 2005 | 11th。リーダーであるFero Griglak (g,key)は、Fermataそのものであるのに、なぜFero Griglak&Fermataと名乗っているのか不明。内容は歌曲と明るいフュージョン。 |
 |
Live V Klube Za Zrkadlom | 2007 | 12作目にして初のライブアルバム。3作目から11作目までのいくつかのアルバムから選ばれた曲が含まれている。ギターがかなり格好良い。 |
 |
Kure v Hodinkach | 1972 | 60年代にビートバンドだった様だが、メンバーチェンジし、木管楽器等も含んだcolosseum的なジャズロックとして発表した唯一のアルバム。いかにもチェコ風のコッテリ感が垣間見られる管・オルガンジャズロック。 |
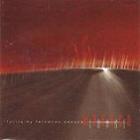 |
Longe | 2004 | 女性ボーカルが魅力的な、なんとも形容しがたいミステリアスなアルバム。ときにバルカン/アラビックなエキゾチックな音楽を奏でる時もあれば、とてもスタイリッシュで映像的な音楽を奏でる時もある。COSなど思い出させられるアバンギャルドな面もあるが、全体的にはジャズロック。傑作。 |
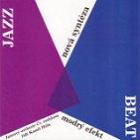 |
nova synteza | 1971 | M Efektと名乗っての1作目。オーケストラ(The Czechoslovak Radio Jazz Orchestra)との共演によるジャズとロックの融合。ギターがロック・ギターだが、ホーンなどが前面に出てきており、ビッグ・バンド・ジャズ風のロック。 |
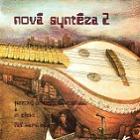 |
nova synteza 2 | 1974 | 2nd。本作も、22分を越える一曲目はThe Czechoslovak Radio Jazz Orchestraとの大々的な共演によるビッグ・バンド・ジャズ風ロック。若干くどさがあるが、ホーンが中心の、スリリングかつドラマティックな演奏と歌が展開される。楽曲の良さが際だつ。 |
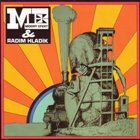 |
Modry Efekt & Radim Hladik | 1975 | 3rd。なぜ、gのHladikが、M Efektと列んでタイトルになっているのか。確かに、前作までのジャズ・オーケストラとの共演ではなく、ヤン・アッカーマンの様に素晴らしメロディを惹きまくるHladikのギターがメインになっている。フルートも少し出てくるし、まるでチェコのフォーカスといった感じのアルバムとなっている。これは傑作。 |
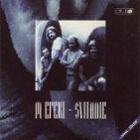 |
Svitanie | 1977 | 前作からb, key(Oldrich Veselyに)が入れ替わって、サウンドはアンサンブル重視の端正なものに変化。静かなパートも多くなっていて、印象は少し地味に。 |
 |
Svet Hledacu | 1979 | gとdsにダブルキーボードという配置で、ベースもシンセサイザーがうなりまくり。イタリアのRustichelli e Bordiniを思い出してしまう。ダイナミックかつドラマティックなアルバム。東欧シンフォニック・ロックの傑作。 |
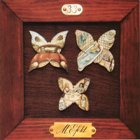 |
33 | 1981 | keyのOldrich Veselyが抜けてしまったが、傾向としては前作の延長。さらに聴きやすい音楽となっている。傑作。 |
 |
Dialog s vesmirem | 1980 | |
 |
Treti Kniha Dzungli | 1982 |
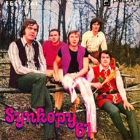 |
Festival | 1972 | ジャケットから見ても分かるように、60年代のビート系の延長線上にあるようなミニアルバム。 |
 |
Xantipa | 1973 | Uriah HeepのEasy Livin' (Demons And Wizards)、Look At Yourselfをカバーしており、オルガン・ハードロックを展開しているミニアルバム。 |
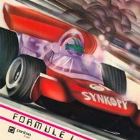 |
Fomule 1 | 1975 | |
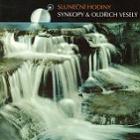 |
Slunecni Hodiny | 1981 | チェコのバンドSynkopy + Oldrich Vesely名義。 |
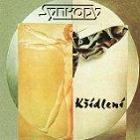 |
Kridleni | 1983 | Oldrich Veselyのひねり出すような歌い方、いかにも東欧らしい重厚感ある演奏で作り上げたシンフォ・ロックのアルバム。 |
 |
Flying Time | 1985 | 前作の延長線上にあるが、英語であるためか、軽快さも同居している。(KridleniのCDのボーナストラックとして本アルバムの大多数の曲を収録) |
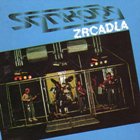 |
Zrcadla | 1986 |
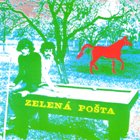 |
Zelen Posta | 1972 | Marian Varga (key)はCollegium Musicumのリーダーであるとともに、平行してソロプロジェクト(これはPavol Hammel-Marian Varga名義)も行っている。 |
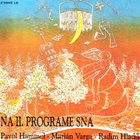 |
Na II. Programe Sna | 1976 | (Pavol Hammel-Marian Varga名義) |
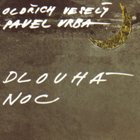 |
Dlouha Noc | 1989 | Modry Efekt、SynkopyのKey |